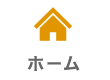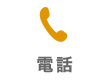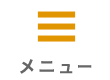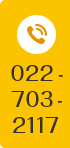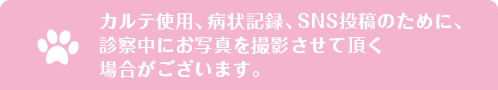歌詞の中で学ぶ
我が家には小さい子がいるため、よく“おかあさんといっしょ”の番組を観ることが多いのですが、子供番組の歌って、ついつい口ずさんでしまうことがあります。
1、2回聴いただけで覚えられる曲。作ってる人は凄いなぁ!と感心してしまいます。(今流行りのJ-Popはもうほとんど覚えられません😂)
おかあさんといっしょの中で“さがそっ!”という歌があり、子供達も大好きなので車の中などでよく歌うのですが、歌詞の一部に、動物病院で働いているがゆえ(?)、天邪鬼にツッコミを入れたくなる部分がありまして・・・(^_^;)
それが
ねっころがって おおあくびの
ポチのくちのなかの むしばいきん!
という部分。
『なんて夢のないことを言うんだー😫』と言われてしまうかもしれませんが、、、ワンちゃんは虫歯になることはほとんど無いんです👩⚕️ ワンちゃんの口の中は人間と違い、虫バイキン(ミュータンス菌)が繁殖できる環境ではないためです。(もちろん虫歯になる可能性はゼロではありません)
ワンちゃんは、人間のように黒く穴が開く虫歯(齲蝕)にはなりにくいですが、そのかわりトレポネーラ菌などが起こす“歯周病”にはなりやすいんです。
まさか子供の歌の歌詞でそんなツッコミ必要ないですし、 ねっころがって おおあくびの
ポチのくちのなかの ししゅうびょうきん! なんて歌う必要もないですから、私の心の中にそっとしまい込んでおけば良いのですけど、お子さんに『ワンちゃんはあんまり虫歯にはならないんだって!』とお話のネタにしてもらえたら面白いかな?と記事を書いてみました(^^;;
そして虫歯にならないから安心というわけでもなく、歯周病もとてもこわい病気です。
ワンちゃん猫ちゃんは毎食後歯磨きすることがないために2日ほどで歯垢が蓄積し、歯石になってしまいます。
一度ついた歯石は歯磨きでは落とせません。さらに表面についた菌よりも、歯肉の奥深くに入り込んだ嫌気性菌の方が体に悪影響を与えるため、麻酔下で、歯周ポケットの中までしっかり汚れを除去することが最良となります。
麻酔のリスクから、なんとか麻酔なしで処置してほしい。と言う方もいらっしゃいますが、ワンちゃんに恐怖心を与えないためにも、処置を隅々まで丁寧に行うためにも、麻酔下で処置する方が負担も少なくなります。
今では室内飼いのワンちゃんがほとんどを占め、人間とのコミュニケーションも密接になっているからこそ、ワンちゃんのお口の中の健康も維持したいものです。歯周病のひどいワンちゃんのお口の中を顕微鏡で見ると、細菌が多数おり、トリコモナスという原虫がウヨウヨしていることもあります。免疫の弱い小さなお子さん・ご高齢のご家族がいらっしゃる場合は特に、ワンちゃんのお口の中を定期的にチェックし、綺麗にしてあげることをお勧めします。
食器へのこだわり

私の個人的な趣味として、食器を集めるのもその1つなのですが、以前から気になっていた食器がつい先日バーゲンにより値引きされているのを発見し、ずっと我慢していた一品をついに購入することができました😃 時間があるとMaduという大好きな食器屋さんを覗きに行くのですが、不思議なもので、そのお店にある数ある食器の中であるとき語りかけて来るような目線(?)を感じて、ふと手に取り裏を見てみると、なんとこの食器の名前が私と同名だったという奇跡。

まさか自分と同じ名前の食器があるなんて😳という驚きと、食器から訴えてくるような感覚があった不思議体験。食器との出会いも、出会うべくして巡り会う〝縁〟があるのかしら…と思わずにはいられませんでした🙂
さて、食器なんて、ただ食べ物を入れるだけのもの。食べ物を乗せる用途を果たせればそれでOK。なのかもしれませんが、
飲み物も、紙コップに注いだワインよりグラスに注いだワインの方を美味しく感じたり、タッパーに詰めたお弁当より、曲げわっぱに入れたお弁当の方がなんとなく美味しく感じるなんて経験、ありませんか?
食器によって食べ物の印象まで変わってしまうのは、実は人間だけでは無いんです。
特に猫ちゃんの場合、飲み水の容器に好みが出ることが多いようです。 (これは視覚的な問題より嗅覚に寄るものでしょう。)
軽くて、ぶつかったり落としても割れにくいことから、プラスチックの食器というものがよく使われると思いますが、プラスチックの器は臭いがつきやすいため、お水の容器として使っていると臭いに敏感な猫ちゃんは嫌厭してしまうようです。確かに我が家でも、子供たち用のコップとしてプラスチック製のものを使っていますが、たまに自分で使ってみるとなんとも言えない臭いがします。
動物たちにも好まれる食器は〝陶器〟だそうですが、これも個体差があり、ガラス製のものが良いという子や、ステンレスのものが好きな子、 おもしろ動画でもたまに見かけますが、流れるお水しか飲まない!(水道から直接!!)という子もいます。
「うちの子、あまりお水を飲まないのよ…」ということがありましたら、もしかしたら食器が気に入っていないという場合もありますので、ぜひ色々なタイプの器を試してみてあげてください☺️ 食器の問題だけでなく、落ち着いて飲み食いできないということも考えられますので、ゆっくり安心して食事ができる環境を整えてあげることも大切です。
多頭飼いの場合は、同じ食器を使いたくないのよね。ということも考えられます。多頭飼い場合は複数個、器を用意してあげることをお勧めします。
飲む点滴
冬の時期になると色々な甘酒が出回ります(^^) 江戸時代には夏バテ対策としてポピュラーだったという甘酒も、今では冬の風邪対策として飲まれることが多い印象です。
甘酒は“飲む点滴”と言われているように、身体に良い栄養素がたっぷりです。
たとえば疲労回復や、皮膚や粘膜を保護する働きのビタミンB群、お腹の調子を整える食物繊維やオリゴ糖、免疫を向上させるアミノ酸などが豊富に含まれています(^^)
この栄養たくさんの甘酒、ワンちゃん猫ちゃんの手作り食にも使える食材です。特にあまり食べられなくなったシニアの子の食事におすすめです。
もちろん、酒粕で作られた甘酒には微量のアルコールや砂糖が使われているため、もし与えるなら米麹100%の甘酒を使ってくださいね。
(ただし、カロリーが高いことと、果糖・ブドウ糖が多いことからダイエットが必要な子や腫瘍のある子には控えた方が良いでしょう。)
ササミや茹で野菜を小さなダイス状にして甘酒を絡めた手作りご飯は舌触りも滑らかになり、食べやすいと思います◎
甘酒は色々な種類があり、私も今までたくさんの種類の甘酒を試してきましたが、個人的に特におすすめなのが宮守川上流産組合さんで作っている遠野のあまざけ。喉越し良く、爽やかな甘さがあり大好きな一品です。
毎年この時期、アリオで行われる岩手フェアがあると出店しているので、かれこれ4年ほど甘酒求めて買いに出かけています(o^^o) 今年はラベルがおしゃれに変身していました☆
お腹の調子も整え、免疫を高めてくれる栄養素がたっぷり入った甘酒ですから、季節の変わり目にお腹を壊しやすい子の体調管理に定期的に取り入れても良いと思います(*´꒳`*)
今日は七草
今日は1月7日、七草粥を食べる日ですね。
我が家もこの一年の無病息災を祈って、朝に七草粥を作り子供達に食べさせ登園させました。
七草粥に使われる材料として、〝セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロこれぞ七草〟と覚えたように、7つの野草を用いるものだと思っていたら、地方によってだいぶ違うそうで…
例えば雪深い東北地方では七草を摘めないので、ただのおかゆを炊いたり、干し柿や栗を入れた七草粥を食べる地域もあるそうです!
調べてみたら、青森県や秋田県では1月7日に行事を行う地域は少数で、その代わりに小正月(1月16日)にけの汁を食べるそうです。
けの汁というものは、ごぼう、人参、大根、ふき、ゼンマイ、細めの筍、こんにゃく、凍り豆腐、油揚げなどをダイス状に切ったものを味噌味で煮込んだものなのですが、青森市出身の私にとってはとても懐かしい郷土料理です😆 祖母がよく作ってくれた思い出があるのですが、たくさんの具材の旨みがたっぷり入っていてとても美味しい料理です。
さて、懐かしいワードが出てしまったために話が脱線してしまいましたが、この七草粥、ワンちゃんにおすそ分けしても大丈夫かな?と迷われている飼い主さんもいらっしゃるかもしれません。
一般的な上記の七草は特に犬に与えていけない野草ではないため、ご家族に作った分をおすそ分けしても大丈夫です。
ただし、味付けとして塩気を強くしているものや、その他の具材を使用しているもの(例えばネギを入れて炊いたおかゆはもちろんダメ)、甲状腺に異常のあるワンちゃん・猫ちゃんには控えた方が無難でしょう。(アブラナ科の植物に含まれる成分で甲状腺に負担をかけてしまう心配がある場合)
また、どんな食べ物に対してもそうですが、アレルギーの有無がわからない初めて与えるものの時は、少量ずつからスタートすることが大切です。
カツオ出汁や鶏肉の茹で汁で炊いたおかゆだと、ワンちゃんも良い香り香りに誘われてよく食べてくれるかもしれません。炭水化物の取りすぎが心配であれば、ドロドロおかゆでなくても、ご飯入り七草スープのように、水分たっぷりめのものでもいいと思います。
お正月のイベントや、帰省の疲れが取れないまま今日から仕事始めという飼い主さんも多いと思いますが、どうぞお身体お大事に、まずは消化の良いもので内臓を休ませてあげてくださいね。

あのジブリキャラクターの

昨日来院した珍しい犬種のワンちゃんです。
気づく人は、あのジブリの有名な犬のキャラクターに似てると感じるかもしれません。
このワンちゃんは、プチバセット・グリフォンバンデーンという犬種なのですが、ハウルの動く城の“ヒン”という犬のモデルにもなったと言われているそうです。

私も始めて出会う犬種でした!
好みの問題

入院中も、やっぱり体をうんと伸ばしたり、バリバリやったり、ストレスを発散させたいもの。
爪とぎは、手軽に買えるものを与えてみましたが、開けたてなので気持ちよさそうに研いでくれました(^^)
ちなみに、よく目にする爪とぎは段ボール製のものが多いですが、猫ちゃんによって、麻タイプのものが良かったり、玄関マットのようなものが良かったり。
床に置いてあるものよりも、立てかけているものが良かったり。
好みが様々です。
爪とぎと同じように、飲み水を入れる器なんかも好みが分かれるところで、
プラスチックの器がいいという子もいれば、陶器じゃないと飲まないという子もいるし、ステンレスがいいという子もいます。
器の問題ではなく、流れているお水を好むという猫の話もたまに聞きます。(蛇口から直接など)
私達も、同じコーヒーでも紙コップで飲むよりコペンハーゲンのカップで飲んだ方が美味しく思えるとか、バカラで飲むお酒は最高!なんてこと、よく聞く話で、猫ちゃんも一緒なんです(^^)
災害への備えとして
エネルギーちゅ〜る、大好評です(^^)
入院中の猫ちゃんも、美味しそうに食べていました。

エネルギーちゅ〜るは通常のものよりカロリーが高いので、おやつとしてはお勧めしませんが、かさばらないので非常持ち出し用として常備しておくと良いと思います。

人も動物も、災害時は身体的にも精神的にもダメージを受けてしまいます。
日頃からの備えとして、水&食料、その他必要な物資の準備はもちろん、
動物の場合はキャリーやケージでの避難が多いため、普段から安心して(精神的負担無く)キャリー、ケージにいられるよう慣れておく必要があります。
キャリー&ケージは
“動物病院に行くときに入るもの”
“お留守番のときに入るもの”
という使い方が多いと思いますが、
キャリー&ケージ=負のイメージだと、とっさの時になかなか入ってもらえません。
日頃から、オヤツをキャリー&ケージで食べたり、遊ぶ時に使う(例えばボール遊びのときにボールをキャリーの中に投げ入れる、おもちゃを入れる)と良いイメージが定着してくれるので、
いざという時にも抵抗なく入ってくれるはずです。
ちゅ〜るが大好きな子は多いので、このようなしつけを行うときにもとても役立ちます。